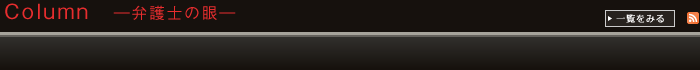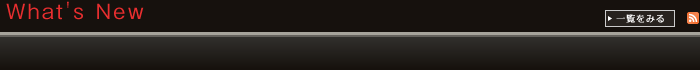2025.03.19
最近の裁判例から
長期間労働により自殺をしたり過労死したり、不幸な例は後を絶ちません。
長時間労働をめぐる問題については、最高裁の判決で、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務があることを認め、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきであり、このことは公立学校に勤務する教員も変わりはないとしています。
ある公立中学校の先生が長時間労働等により精神疾患を発症し自殺したとして、遺族が校長に注意義務違反があったとして市を相手に裁判を起こしました。
本件では、長時間労働を余儀なくなされた理由が、この亡くなられた先生が吹奏楽部の顧問を担当していたことにあったようです。この学校はこの方が顧問に就任する前から、後援会があり、その活動はコンクール以外にも多く企画され、高いレベルを目指して活動するための仕組みが既に存在し、吹奏楽コンクールの全国大会出場、金賞獲得という目標は、学校全体の目標となっていました。
こうしたことから、この部活動は、単なる課外活動ではなく、業務の一環として組み込まれており、これを校長も容認し、校長において黙示の業務命令があったと裁判所は判断しました。
当事務所は、こうした長時間労働の問題も扱っておりますので、ご相談下さい。
(八十島 保)
2025.02.03
最近の裁判例から
いわゆる医療事故の裁判です。患者さんは58歳の税理士でした。
この方は最初腰痛の治療のため相手方病院を受診していたところ、手足に痺れの症状が出るようになり、頚椎椎間板ヘルニアと診断され、頚椎椎弓形成術を受けたところ、術後、視力及び視野機能が低下する事態となりました。
患者側は、腹臥位(うつ伏せで顔を横に向けた状態のことです)で、椎弓形成術を行う場合、視神経や網膜への血流低下により、重大な視力障害を引き起こす可能性があることから、血流低下を予防する措置を講じる義務があるのに、これを怠った過失があると主張しました。
これに対し、病院側は血流低下を予防する措置は講じていた、本件は血流低下によって生じたのではなく、原因不明の視神経炎によるものだと主張して争いました。
この裁判は、カンファレンス鑑定が実施されています。医療事故の裁判では、医学的知見見基づく判断が必要であることから、鑑定が実施されることがあります。その場合は、一人の鑑定人が書面を作成し裁判所に提出するという方法で実施されます。
この制度は、鑑定人の負担が重い、一人の鑑定人の判断で客観性が確保されるのか等といった様々な問題が指摘されていました。
そこで東京地裁では、カンファレンス鑑定といって、複数の鑑定人を選任し、簡潔な意見書の作成を依頼するとともに、裁判期日において、口頭で議論しながら意見をまとめます。
この裁判ではカンファレンス鑑定の結果を踏まえ、患者側の主張が認められるという結果に終わっています。
当事務所は、医療事故に特に力を入れておりますので、ご相談下さい。
(八十島 保)
2024.12.26
最近の裁判例から
平成30年の民法改正で、新たに民法第1050条に特別寄与料という制度が設けられました。
これは、相続人ではない被相続人の親族が(例えば被相続人の奥さんなど)被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合、その貢献に応じた額の金銭の支払いを請求できることになりました。
この制度ができるまでは、例えば相続人である夫に代わって被相続人である夫の親の療育看護に努めたとしても、妻は相続人ではないので遺産の分配を受けられないという不公平が生じていました。
さて、今回ご紹介する裁判は、被相続人が、二人いた子のうち、一人に全財産を相続させるという遺言をしていた(もう一人の相続人であった被告には相続分がないことについては、争いはありません)場合に、唯一の相続人である子の妻が、特別寄与料の負担を、相続人ではなくなった者、即ち被告に請求できるかが争われました。
被告は、遺留分侵害額請求権を行使したことから、遺留分として財産をもらうのであれば、相続人の妻は、特別寄与料も負担すべきだと考えて、このような裁判を起こしたものと思われます。
この争いは、最高裁まで持ち込まれ、最高裁は妻の請求を認めませんでした。
その理由は、民法1050条の5項で、相続人が数人ある場合、各相続人の特別寄与料の負担割合は、法定相続分によることとされていることからすると、相続分がない以上、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当としました。
当事務所では、相続に関する相談をお受けしておりますので、是非ご相談下さい。
(八十島 保)
2024.12.25
年末年始の休業について
本年の営業は12月27日(金)正午までとなります。
新年は令和7年1月7日(火)午前9時より営業します。
2024.08.08
夏期休業のお知らせ
令和6年8月13日(火)・14日(水)は休業させていただきます。
2020.05.11
新型コロナウイルスの影響について
事業者の皆様は、現在の新型コロナウイルス及びこれに伴う緊急事態宣言により、多大な影響を被っておられると思います。
このような時には、収入を確保し、支出を抑制し、正常に戻るまで資金繰りの目途をつけることが一番重要です。
その入りと出について、お悩みはありませんか。金融機関や取引先との交渉がうまくいかないということはありませんか。またそもそも資金繰りをどのように確保してよいか悩んではいませんか。
これまで弁護士に相談したことがない方もこのような緊急事態ですので、是非、我々弁護士を利用してみて下さい。
この関係の相談には、相談料無料で対応します。